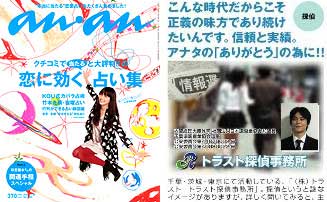日本文学が世界で再び注目を集めている中、英語圏で高い評価を受けている翻訳小説のひとつが、川上未映子の『ヘヴン』です。原作は2009年に日本で出版され、2021年にサミュエル・ベッツによって英訳されてからは、ニューヨーカーやガーディアン紙などでも取り上げられ、英語圏の読者の心を捉えました。

『ヘヴン』とは? 探偵のように読み解く物語
『ヘヴン』は、学校でいじめを受ける14歳の「僕」と、同じくいじめられている少女コジマの静かな交流を描いた物語です。物語自体に明確な「探偵」や「事件」は登場しませんが、読者はまるで探偵のように登場人物たちの心の謎を読み解いていくことになります。
なぜ「僕」は反抗しないのか? なぜコジマは耐え続けるのか? この物語には、多くの問いが散りばめられており、それを一つひとつ読み解く過程が、ミステリー小説を読む体験にも似ています。人の心の奥底にある“見えない動機”や“真実”を探るという点で、『ヘヴン』は心理探偵小説とも呼べる側面を持っています。
浮気のような心の逃避と共犯関係
『ヘヴン』の「僕」とコジマは、いじめという過酷な現実から逃れるように、互いに手紙を交わし、密かなつながりを育んでいきます。このやり取りは、ある意味で**現実への“浮気”**のような行為です。家庭や学校という「正しい場所」から感情を逸らし、心の拠り所を別の場所に求める行為。それは、恋人がいるにもかかわらず、別の人に心を寄せる浮気に似た感覚を与えます。
このように考えると、『ヘヴン』はただの青春小説ではなく、人間がいかにして「心の逃げ道」を探し、時には道徳やルールから外れてでも“生き延びよう”とするかを描いた作品ともいえるでしょう。
英語圏での反響とその理由
英語圏では、村上春樹をはじめとする日本文学が一定の人気を持ち続けていますが、川上未映子のような新世代の作家の登場は、日本文学の幅を広げています。『ヘヴン』の英訳は、「いじめ」というユニバーサルなテーマに対し、詩的で内省的な文体が高く評価されました。
特に、morality(道徳)とcomplicity(共犯)**というテーマが、西洋の読者にとって新鮮だったといわれています。被害者が必ずしも「善」ではないという複雑な描写や、沈黙を守ることで生まれる共犯関係が、読者に深い問いを投げかけるのです。
まとめ
『ヘヴン』は、探偵のように他者の心を探り、浮気のように日常から逸れながら、真のつながりを探す物語。その深層にあるメッセージは、日本語でも英語でも変わらない力を持っています。